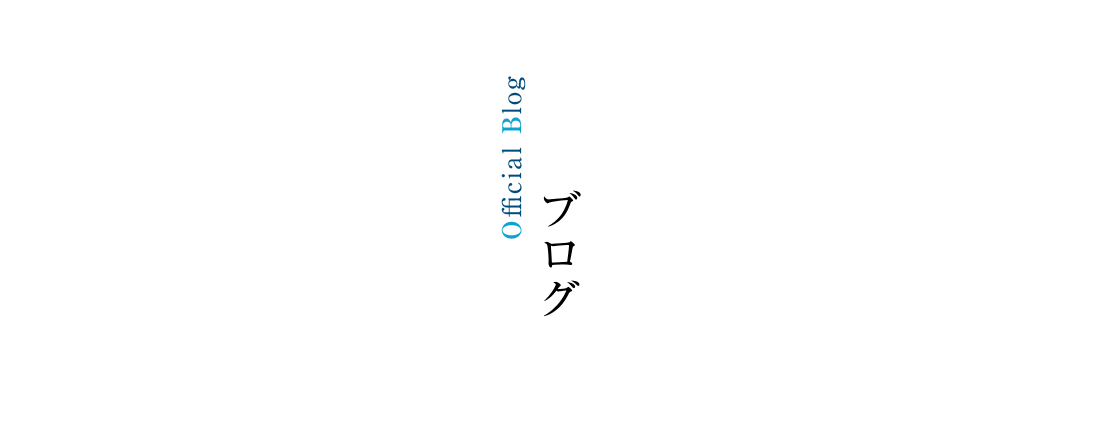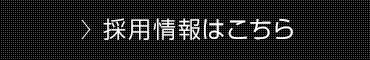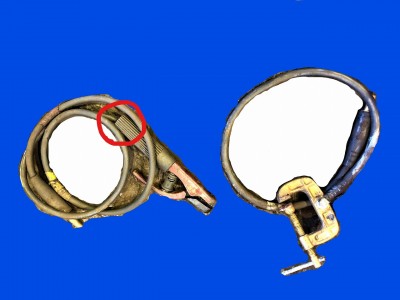-
最近の投稿
カテゴリー
- シャックル
- ナイロンスリング
- 玉掛け用ワイヤーロープ
- チェーンブロック
- レバーブロック
- ギヤードトロリー
- 道工具
- 日記
- 手話
- TIG溶接
- アルゴンガス
- 溶接用アース 磁石式
- TIG溶接用ケーブル
- TIG溶接棒
- タングステン
- トーチ
- TIG溶接機
- 指文字
- 極薄ゴム手袋
- 豚革手袋
- 防振用手袋
- 耐切創手袋
- 薄手のゴム手袋
- 耐油性厚手のゴム手袋
- 革手袋
- 軍手
- 美術
- クイズ
- 正解
- モールス信号
- アーク溶接
- 溶接棒
- 溶接機
- 溶接用アース
- 溶接用ホルダー
- アースクランプ
- 溶接面
- キャブタイヤ
- ガス溶接 ガス溶断
- ガスホース
- ガスライター
- 酸素ボンベ
- アセチレンボンベ プロパンボンベ
- ガス切断器
- ガスメーター
- ディスクグラインダー
- 砥石
- 切断砥石
- 作業服
- 作業用靴下
- 保護メガネ
- 安全靴
- ヘルメット
- 防塵マスク
- 安全帯
- フルハーネス型安全帯